こんにちは、クレイジースタディ管理人のじきるうです。クレイジースタディはこれまでに200本以上のおもしろ記事を配信してきました。
今回はその経験をもとに、多くの人に楽しんでもらえる「おもしろい記事」の企画づくりについて、7つの原則をご紹介します。
原則1. おもしろいことが書いてある
おもしろ記事は「何かしらのおもしろいことが行われている・話されている記事」です。そりゃそうだよね!
ただし、おもしろの定義はケースバイケースです。ざっっっっっくり大別すると、おもしろい記事には以下の2種類があると考えています。
- Funny(Laugh)系
あたまを空っぽにしてガハハと読める記事- Interesting系
知識欲が満たされるような役に立つ記事
大切なのは、筆者が見て、読者が見て、何かしらの視点で「おもしろい」と思えるかどうかです。逆に言うと、自分ですらおもしろいと思えない記事は、誰が読んでもおもしろくありません。
またもう一つ大切なのが、読者に得をさせること。
「この記事を読んでよかった!」と思ってもらうために、読んだ後にポジティブな感情を生むことが大切です。有益な情報を提供したり、とにかく笑える記事を提供したり……その方法は自由です。「何の得にもならないムダな記事」はNG。時間をつくって読んでくれた読者を、がっかりさせないように心がけましょう。
たとえばこちらはFunny(Laugh)系の記事。タイトルどおりの内容ですね。何も考えずあたまを空っぽで読める、塩分濃いめの記事に仕上がってます。
この記事はInteresting系ですかね。マツケンガチ勢が語ったマツケンシリーズ解説の記事。そもそもマツケンガチ勢っているんだ……!? この記事を読むだけで、周りの人よりマツケンに詳しくなれます。
原則2. 企画はシンプルに
前提の説明が長い記事は、読まれません。シンプルに説明できる企画を心がけましょう。
シンプルな企画とは、つまり「わかりやすい企画」です。いまは情報に溢れた時代なので、複雑なものはそもそもスルーされてしまいます。
目安として、以下の2つのポイントがあると考えています。
- タイトルを見て3秒で理解できるか?
タイトルを見て3秒以内に理解できない企画は、再考したほうが良いかもしれません。なおTwitterの場合、ユーザーは1ツイート当たり1.08秒しか見ていないという研究もあります。1秒でユーザーの心をつかむタイトル……厳しい時代ですね!- 記事冒頭300字で企画を説明できるか?
多くの記事では、冒頭で企画の説明をすることになると思いますが、そこが長ったらしいと読者は読むのを諦めてしまいます。冒頭300字くらいで説明を終わらせましょう。
こちらは5文字で伝わるタイトルですね。「無言飲み会」でどんな内容かを表しつつ、「ふだんはガヤガヤうるさい飲み会を無言でやったらどうなるんだろう……?」と興味をひいています。
上の記事もシンプルでわかりやすい企画だと思います。また冒頭259字で企画の説明がなされており、スルッと読めてしまいます。
原則3. 多くの人が楽しめる
多くの人が、それを読んで「おもしろい」と思えるかどうかは大切です。
読者ターゲットを絞った記事であればその限りではありませんが、内輪ネタや極端にローカルな話題など、一部の人にしか伝わらないテーマは扱いが難しい傾向にあります。かといって、間口の広いテーマを無闇矢鱈と取り上げても、平凡な記事ができ上がる恐れがあります。
間口の広いテーマ/狭いテーマそれぞれの扱いは、以下のようにするのがおすすめです。
- 間口の広いテーマ
グルメ、なつかし、時事ネタ、あるある、日常で使うもの、家族など
➡︎そのまま使うと凡庸な記事になりがち
➡︎すこし捻ったキャッチーな切り口を合わせる- 間口の狭いテーマ
路線図、肩手袋、武蔵嵐山駅、モクズガニなど
➡︎素材がニッチなので、そもそも興味を持たれにくい
➡︎知らない人でも興味をそそる切り口を主題にする
「テーマ」と「切り口」の、どちらかをマスに、どちらかをニッチにすると上手くいくことが多いなと感じています。
なつかし系の王道テーマ・読書感想文を、スピードで競わせるという企画です。
「読書感想文(テーマ) × 邪道バトル(切り口)」という組み合わせ。読書感想文を “邪道な手法” と戦わせる発想は、興味をそそられませんか?
こちらは広島県広島市に存在した私設図書館を取材した記事です。ローカルかつニッチな本屋なのですが、昭和のエロ本の蔵書が多いことで話題になっていました。
「ローカル私設図書館(テーマ) × 昭和のエロ本レポート(切り口)」という企画で、読者の興味をひいています。
原則4. ライター本人が楽しめる
大前提ではありますが、書くテーマはライター本人が楽しめるものにしましょう。ライターが楽しんで書いてるかどうかは、読者に伝わります。
書いてる本人が楽しめない記事は、誰が読んでも楽しめません。自分自身が本気で楽しめるテーマを設定しましょう。
ポイントは以下の2つです。
- 自分自身の体験を加えられるか
- 自分ならではの視点を加えられるか
たとえば、コンビニのおにぎりを毎日1つ以上、1年間食べ続けてる人が書いた「おすすめのコンビニおにぎり」という記事があったら、読みたくなりますよね。ライター本人もコンビニおにぎりについて詳しく、言いたいこともたくさんあるはずなので、楽しく書けるはずです。
なお、記事を書いている途中でふと我に返って、ついネガティブな感想を書いてしまうこともありますが、「くだらないことをしてしまった」などと書くと、読者ははしごを外されたような気持ちになります。最後まで突っ走って、楽しんで書くことも大切です。
上の記事は、ライター自身が全編とおして非常にいい表情をしています。アイキャッチ(サムネイル)だけでも十二分に伝わりますよね。楽しんで体験・実行したからこその、この笑顔だと思います。
普段からダルマを持ち歩き、ダルマ専用のInstagramアカウントまで開設しているライターによる記事。そんな彼だからこそ書ける内容に仕上がっています。
原則1でも例を先述しましたが、何かのガチ勢が書いた記事はたいていおもしろくなります。
もう少しとっつきやすい例を挙げるなら、こちらの記事でしょうか。スーパー戦隊を愛する主婦が書いた、おすすめ作品と鑑賞ポイント、物申したい点をまとめた企画です。
ふだんからよく触れている、好きなものについて書くと、全く知らないものを書くよりはおもしろくなりやすいです。
原則5. その記事を書く理由がある
読む人が納得できる、取り組む理由があるテーマを選びましょう。ちょっとややこしいので、具体例を出して説明しますね。
たとえば以下のような企画を考えたとします。
「チャリで100km先の温泉にいってみた!」
しかし、ただチャリをこいで遠くの温泉に行くだけの記事は、なぜそれをやるのか理由がなく、読者の共感が得られません。
理由がない → 意味がわからない → 共感ができないからです。
「うるせぇ! 俺はこのネタがやりたいんだ!」という衝動も大事ですが、読者を置いてけぼりにしてしまう恐れもあります。「私たちは何を見せられてるんだ?」とポカンとしてしまうかもしれません……。(めちゃめちゃな熱意を伝えられれば例外はあります)
では上記のテーマにすこし手を加えて、以下のような企画ならどうでしょうか。
「 “疲れた時に入る温泉 = 最高” を証明するために、チャリで100km先の温泉まで走ってみた!」
疲れた時に入る温泉って、気持ちいいですよね? ならば、めちゃめちゃ疲れた時に入る温泉は、天にものぼるような気持ちになるのでは?
なかなか無理やりなこじつけではありますが……なんとなく納得できそうな理由をつけると、読者は共感しやすくなります。
なお、この企画は実在します。ありがたいことに、デイリーポータルZで新人賞(佳作)をいただいた記事でもあります。……こういう実績のある記事だと、紹介しやすくていいですね。
「甲子園を見ていて思ったけど、どの学校の校歌もだいたい同じようなこと言ってるんじゃね?」
↓
「それなら、全国の校歌で使われているワードを組み合わせたら、日本一平均的なそれっぽい校歌ができるんじゃね?」
という発想で作られた企画。そのとんでもない労力もさることながら、何かしらの理由づけがあると読者はスッと記事の世界に入れます。
なお、こちらの記事はオモコロ杯で銅賞を受賞しました。
こちらは最悪な例です。(※管理人が書いた記事です)
「マスクが似合うスポーツ」という、どこに需要があるかわからない内容ですね。しかもなぜこの記事を書いたかを「うるせ〜〜〜〜〜!!!!」で誤魔化してます。理由もクソもありません。出直してください。
原則6. 手を抜かない
これ、書こうかどうか正直迷いました。人はどうしても楽な方向に流れるので、これは仕方のないことなんですよ。
でも、手を抜いたら箇所って絶対バレるんです。読んでて違和感というか、「そこもう少し深堀りしてほしかったなぁ……!」という箇所がかならず見つかります。逆にいうと、「そこまでやるの!?」と思われるような “やりきった記事” は、かならず評価されます。少なくとも、ボクは評価します。
「どれくらい手間をかければいいのか?」の基準を提示するのはなかなか難しいですが……すくなくとも、企画実行から記事を書き切るまでに、最低3時間はかけたほうがいいかなと考えています。
また企画そのものの作り込みだけではなく、「そのときどう思ったか」「身体の反応はどうだったか?」「たとえるならそれはどんな感覚か?」「それを見ている人はどんな反応だったか?」など、文章の表現にこだわる時間も大切です。
……念のため補足ですが、「手を抜かない=記事を長くする」ではありません。手はかけつつも、読者の読みやすいように適宜カットや推敲を重ねるのがおすすめです。
たとえばこちらの記事。普通なら、煮込みラーメンの魅力やおすすめのアレンジレシピを紹介するくらいで終わっちゃうんですよね。
しかし上記の記事は、永谷園HD広報にわざわざ問い合わせて「過去の煮込みラーメンのパッケージ18年分」を取り寄せ、それぞれのパッケージや味展開に関する考察まで行ってます。ここまで書かれたら「うわー! やられたわー!」と諸手挙げて降参です。
こちらの記事はタイトルからも分かるとおり、エグい数の調査をしてますね。
なお、ライターは現役のITエンジニアでもあるのですが、そのプログラミングの技術を活かして116万人分のデータを集めたそうです。
自分の持っているスキルは、記事にどんどん活かしていきましょう。思わぬ飛び道具となるかもしれませんよ。
こちらはパッと見、ただのまとめ記事なのですが、まとめてる数が異常ですね。ちなみにクレイジースタディで最近もっともアクセスの多い記事がこれです。
たとえプログラミングのような特殊スキルがなくても、このように異常なほどの労力をかけることで評価されることはあります。
原則7. 誰かを傷つけるものではない
誰かを傷つける記事は、ぶっちゃけよく読まれます。
世の中、ポジティブな話題よりネガティブなニュースが目立ちますが、それは数字が伸びやすいからです。誰かを傷つける記事には批判が生まれ、それがSNS等での言及となり拡散されやすいんですよね。悪意は拡散されます。
しかしそれは、ある種の炎上商法であり、ダメージはいずれ自分に返ってきます。
そもそも、誰かを傷つける記事は、読んでいて明るい気分になりませんよね。おもしろメディアの管理人として、これを「おもしろい」と言うわけにはいきません。
なおここで注意したいのが、「無意識に人を傷つけてしまうことがある」という点です。
たとえば「ホームレスにご飯をあげてみた!」「宗教勧誘を撃退してみた!」のようなネタは、たとえあなたがおもしろいと思っても、絶対にやめましょう。それで生計を立ててたり、信念を持ってやっている人がいる以上、茶化すべきではありません。
こちらはクレイジースタディ管理人がメディア立ち上げ初期に書いた、インタビュー記事。かなりセンシティブなテーマなので、慎重に、フラットな視点でのぞむ必要がありました。(※筆者は創価学会となんの関係もありません)
まとめ
【おもしろ記事 7原則】
- おもしろいことが書いてある
➡︎ 自分でおもしろいと思えない記事は、誰が読んでもおもしろくない- 企画はシンプルに
➡︎ 前提の説明が長い記事は読まれない。3秒で理解できる企画を考えよう- 多くの人が楽しめる
➡︎ 「テーマ×切り口」の組み合わせで、多くの人に興味をもってもらえる企画を考えよう- ライター本人が楽しめる
➡︎ 書いてる本人が楽しめない記事は、誰が読んでも楽しめない。まずは自分自身が本気で楽しもう- その記事を書く理由がある
➡︎ 読む人が理解できる、そのネタに取り組む理由を考えよう- 手を抜かない
➡︎ 手を抜いた記事はバレる。やりきった記事は評価される- 誰かを傷つけるものではない
➡︎ 誹謗中傷を含む企画は、明るい気分にならない
最後にはなりますが、これら7原則は「絶対」ではありません。実際クレイジースタディにも、この原則から外れた記事はたくさんあります。
ただ、これらを意識して記事制作を行えば、そんなに間違った方向には行かないんじゃないかな、とも考えています。
記事企画をつくるときの、参考になれば幸いです。
(執筆:じきるう)

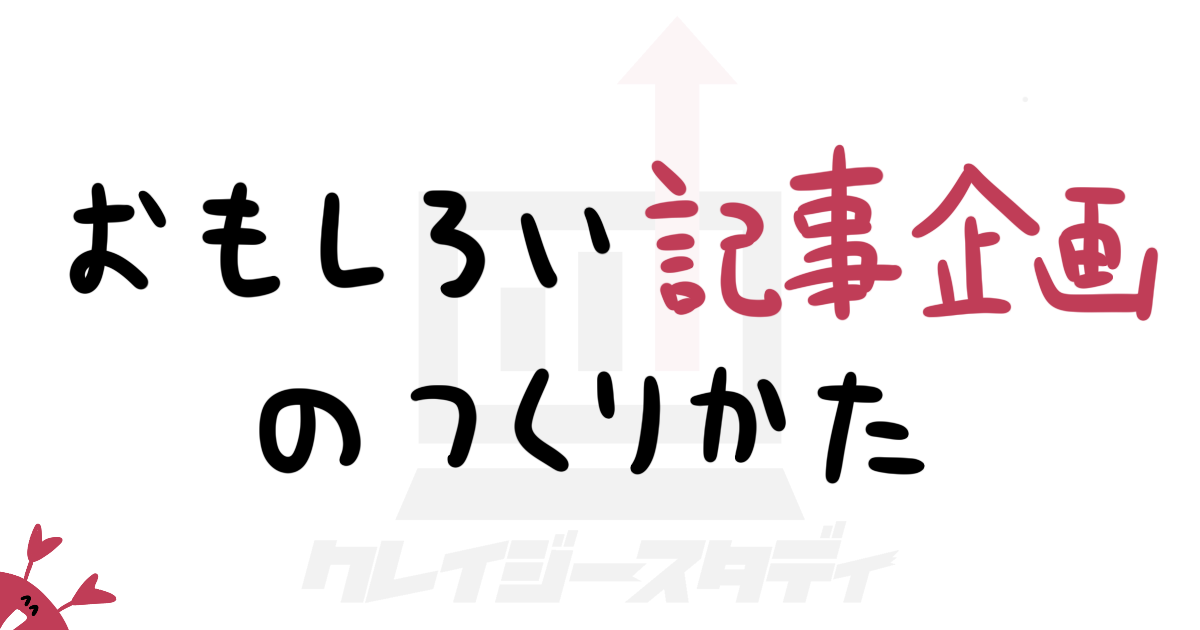
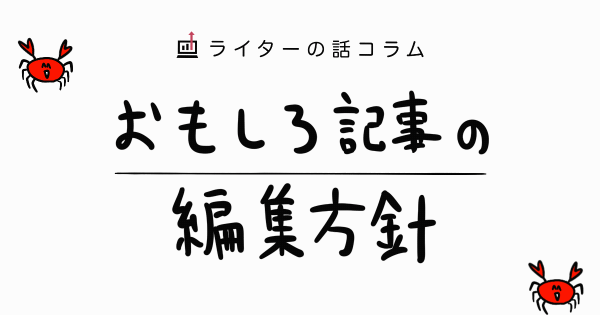
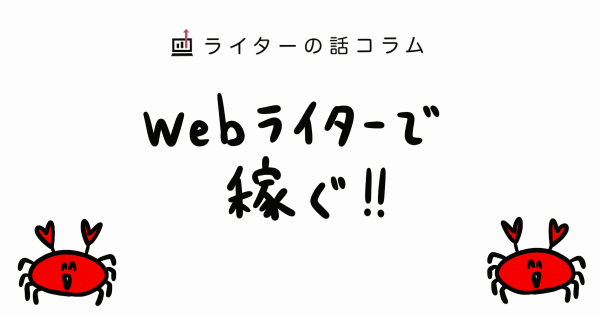





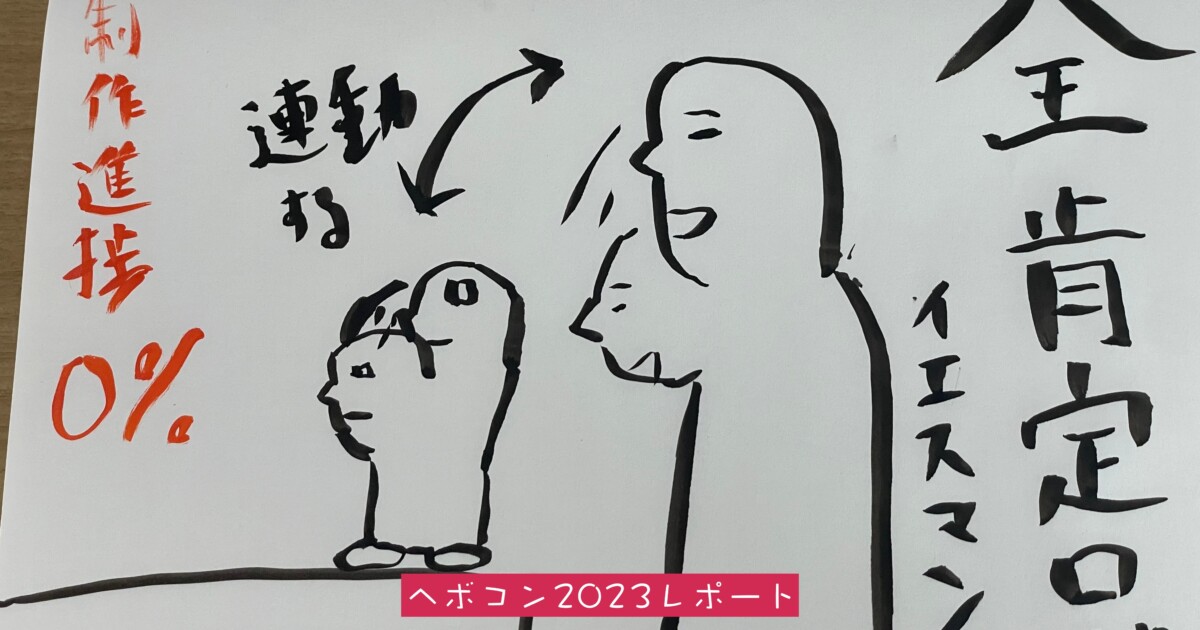





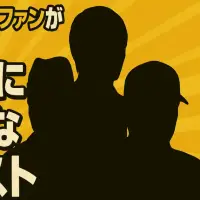 年間人気記事ランキング2025
年間人気記事ランキング2025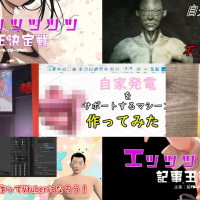 年間人気記事ランキング2024
年間人気記事ランキング2024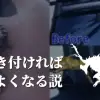 年間人気記事ランキング2023
年間人気記事ランキング2023 年間人気記事ランキング2022
年間人気記事ランキング2022 年間人気記事ランキング2021
年間人気記事ランキング2021 年間人気記事ランキング2020
年間人気記事ランキング2020 年間人気記事ランキング2019
年間人気記事ランキング2019 年間人気記事ランキング2018
年間人気記事ランキング2018 エッッッッッッッ記事王決定戦
エッッッッッッッ記事王決定戦 狂気記事王決定戦
狂気記事王決定戦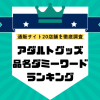 こたつ記事王決定戦
こたつ記事王決定戦